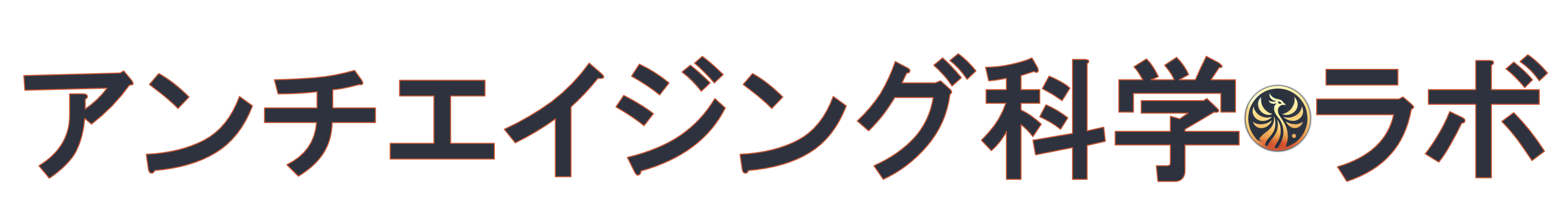認知症予防の新たな展望:認知症は約50%が予防できる⁉
近年、認知症の予防や治療に関する研究が進み、多くの新しい知見が明らかになっています。2024年にLancet誌に発表された論文によると、認知症予防の可能性がさらに拡大し、新たなリスク因子や介入方法が提唱されました。本記事では、認知症の予防について解説します。
認知症は予防できる?
認知症は、適切な対策によって約50%が予防または発症を遅らせることが可能性であることが分かってきました。これまでの研究で、認知症のリスク因子となる生活習慣や疾患が判明しています。現在、分かっているのは次の14が主要なリスク因子です。
【認知症の14のリスク因子】
- 教育歴が少ない
- 聴力の低下
- 高LDLコレステロール
- うつ病
- 頭部外傷
- 身体活動の不足
- 糖尿病
- 喫煙
- 高血圧
- 肥満
- 過度のアルコール摂取
- 社会的孤立
- 大気汚染
- 視力の低下
(Livingston et al., 2024)

これらのリスク因子を適切に管理することで、認知症の発症リスクを大幅に低減できるとされています。
認知症予防のためにできる具体的な対策
リスクを軽減するための具体的な方法について、次のことが提案されています。
- 教育の充実と生涯学習の促進
幼少期からの教育は、脳の認知予備能を高め、将来的な認知症リスクを減らします。認知予備能とは、脳が加齢や疾患によるダメージを受けても適応し、脳機能を維持する能力のことです。たとえば、神経細胞が損傷を受けても、脳が別の経路を使って機能を補うことで、認知機能の低下を遅らせることができます。
認知予備能は、学習、読書、パズル、音楽、芸術、社会活動などの知的刺激によって強化されることが示されています。また、大人になってからも新しい知識を学ぶことや、日常的に脳を使う活動を続けることで、認知症のリスクを軽減できます。 - 聴力の維持と補聴器の使用
加齢による聴力低下は、認知症のリスクを高めることが分かっています。しかし、補聴器を適切に使用することで、このリスクを大幅に軽減できる可能性があります。特に、難聴がある人が補聴器を使うと、認知機能の低下が遅くなることが示されています。
また、難聴を予防することも重要です。日常的に大音量で音楽を聞く、騒音にさらされているなど、聴覚に負担をかけている人は注意が必要です。聴力を維持するために、定期的な聴力検査を受けることが推奨されます。 - 高血圧とコレステロールの管理
高血圧や高LDLコレステロール(悪玉コレステロール)は、脳の血管にダメージを与え、認知症リスクを高めます。40歳を過ぎたら、血圧を130mmHg以下に維持することが推奨されており、適切な食事や運動、必要に応じた薬物療法で管理することが重要です。 - 喫煙をやめ、飲酒を控える
喫煙は脳の血管に悪影響を与え、認知症の発症リスクを高めることが分かっています。喫煙をしている人は、今すぐに喫煙をやめてください。
過度の飲酒も脳細胞にダメージを与えます。特に、週に168 g以上のアルコール摂取(350mlの缶ビール1缶に換算すると約12杯)は認知症リスクを増加させるため、適量を守ることが大切です。 - 定期的な運動
運動は脳の健康を維持するために重要です。ウォーキングやランニング、水泳など、週に150分以上の中等度の運動を行うことで、アルツハイマー病などの認知症のリスクを低減できます。また、運動を習慣化することでストレス軽減にもつながります。 - 社会的なつながりの維持
家族や友人との会話や交流、地域の活動に参加することは、脳を活性化させ、認知症リスクを下げることが示されています。社会的に孤立すると、認知機能の低下が早まる可能性があるため、積極的に人との関わりを持つことが推奨されています。 - 視力低下の管理
視力低下は認知症の新たなリスク因子のひとつとされ、未治療のままだと認知症リスクが高まる可能性があります。定期的な眼科検診を受け、必要に応じてメガネやコンタクトレンズ、白内障手術などの治療を行うことが重要です。 - うつ病の早期治療
うつ病は、脳の機能に影響を与え、認知症のリスクを高める可能性があります。抗うつ薬の使用やカウンセリングなど、適切な治療を受けることで、認知症の発症を抑えることができる可能性があります。 - 大気汚染の低減
大気汚染は脳に悪影響を及ぼし、認知症のリスクを高めることが報告されています。特に、都市部に住む人は大気汚染の影響を受けやすいため、外出中はマスクをしたり、室内では空気清浄機を活用することが推奨されます。 - 頭部外傷の予防
頭部外傷は認知症リスクを高める可能性があります。頭に衝撃を受けると、脳にダメージが蓄積し、認知症リスクが高まります。スポーツ(特にラグビーやアメフト、ボクシングなど)や事故による頭部外傷を防ぐため、適切なヘルメットを着用することや、安全対策を徹底することが重要です。
認知症になると…
認知症になると、症状によりますが記憶力や判断力の低下、感情のコントロールが難しくなるなど、日常生活をおくることが困難になります。さらに、本人だけでなく家族や周囲の人にも影響がでます。
また、経済的な影響も大きくなります。少し前のデータになりますが、2018年度の日本におけるアルツハイマー型認知症による経済負担は、
- 総医療費:1兆730億円/年(内訳:薬剤費が1,510億円/年、薬剤以外が9,230億円/年)
- 公的介護費:4兆7,830億円/年
- 生産性損失額:1兆5,470億円/年
なお、1人当たりに換算すると、年間で約200万円の経済負担が生じることになります。
まとめ
認知症の予防可能性がより明確になり、リスク因子の管理が生涯を通じて重要であることが示されました。一度に全てを対策することは困難かもしれませんが、できることから一つ一つ対策していくことで、着実に認知症の予防につながります。
「認知症は予防できる病気である」という考えが、今後ますます浸透し、多くの人々が自らの健康を積極的に管理することにつながることを期待しています。
参考文献
Livingston, G., Huntley, J., Liu, K. Y., Costafreda, S. G., Selbæk, G., Alladi, S., … Mukadam, N. (2024). Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. The Lancet, 404 (10361), 572–628. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01296-0
Ikeda, S., Mimura, M., Ikeda, M., Wada-Isoe, K., Azuma, M., Inoue, S., & Tomita, K. (2021). Economic burden of Alzheimer’s disease dementia in Japan. Journal of Alzheimer’s Disease, 81(2), 309–319. https://doi.org/10.3233/JAD-210075