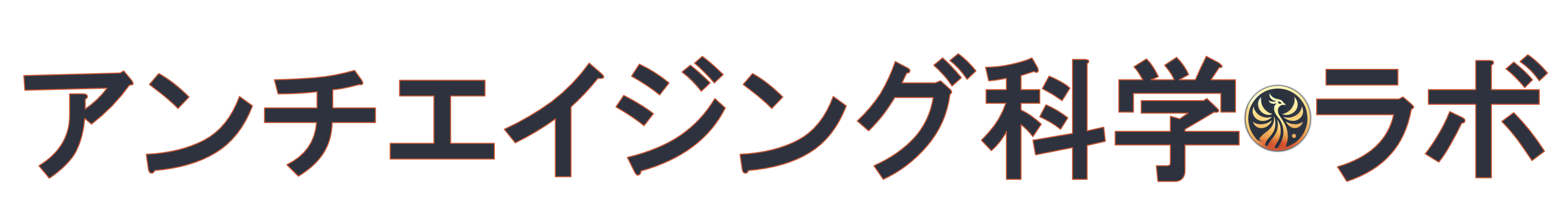人とのつながりが脳を守る?“孤立”と脳萎縮の関係
「最近、人と話す機会が減ったな…」「年を重ねるごとに、外に出るのが億劫になってきた…」
そんな日々の何気ない変化が、脳の構造にまで影響しているかもしれません。
2023年に発表された日本発の大規模研究によって、社会的なつながりの頻度と脳の萎縮との間に深い関係があることが明らかになりました。
🔍 どんな研究?
この研究は、全国の65歳以上の高齢者約9,000人を対象に行われたものです。
研究チームは、「どれくらい人と接触しているか」(家族以外の友人や親戚との会話頻度)と、脳の状態(MRIで測定)を分析しました。
接触頻度は「毎日」「週に数回」「月に数回」「ほとんどなし」の4段階に分類され、全体の脳の大きさや、記憶や感情に関わる重要な部位(海馬や扁桃体など)の体積との関係が調べられました。
📊 結果は…「人と会わないほど脳が縮んでいた」
研究の結果、社会的接触が少ない人ほど、脳の広い範囲が萎縮していることがわかりました。具体的には:
・ 全体の脳体積が小さくなっていた
・ 記憶・感情・社会的認知に関わる部位(海馬、扁桃体、側頭葉など)が特に萎縮していた
・ 大脳白質病変が多かった
※大脳白質病変:脳深部の大脳白質(主に神経線維が存在する部位)に生じた虚血性変化(栄養を送る血液の流れが不足したことで生じた変化)
という驚きの事実が明らかになったのです。
😔 それ、うつのせいでは?
実際、「人と会わないこと」と「うつ傾向」の関係は深く、研究でも一部は抑うつによって説明できることが示されました。
しかし注目すべきは、脳の萎縮の70%以上は、うつ以外の理由で説明されるという点です。
つまり、“人と関わること”そのものが、脳の健康にとって非常に重要なのです。
🧠 なぜ“人と話す”だけで脳が守られるのか?
今回の研究では、次のような可能性が考えられています:
・ 会話は“脳の筋トレ”:聞く・話す・考えるを同時に行う高度な作業
・ 外出や移動が増える:身体活動や環境刺激が脳に好影響
・ 感情の共有でストレス軽減:孤独感や不安が和らぎ、脳の炎症が抑えられる
・ 話題を通じた記憶刺激:過去の経験や知識を思い出すことで海馬が活性化
✅ 今からできる“脳に効く”習慣
・1日1回、誰かと話す時間を意識する(電話でもOK)
・昔の友人に連絡してみる
・買い物や公園でのちょっとした会話も大切に
・地域の集まりやサークルに参加してみる
まとめ:脳を守る“特効薬”は、人とのつながりかもしれない
この研究は、社会的接触の頻度と脳の萎縮とがはっきりと関連していることを、科学的に証明した貴重な成果です。
「最近、人と話してないな…」と感じたら、それは脳のSOSかもしれません。
1日数分の会話が、あなたの脳を若々しく保つ鍵になるかもしれません。
「 今日、あなたは誰と話しましたか?」
スマホを手にとって、まずは一人に声をかけてみてください。
それが、未来のあなたの脳を守る第一歩になるかもしれません。
Hirabayashi, N., Sugiura, M., Aida, J., Tsuji, T., Koyama, S., Yamaguchi, M., … & Osaka, K. (2023).
Association between frequency of social contact and brain atrophy in community-dwelling older people without dementia: JPSC-AD neuroimaging study.
Frontiers in Aging Neuroscience, 15, 1192576. https://doi.org/10.3389/fnagi.2023.1192576