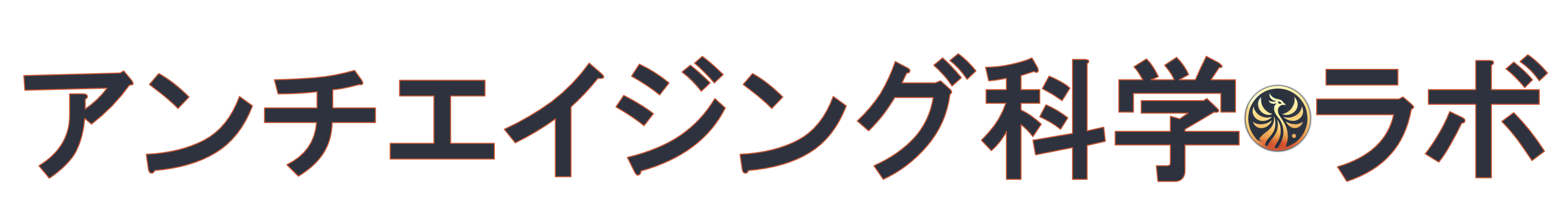早起きしすぎると脳が縮む?睡眠と脳の意外な関係
「早起きは三文の徳」と言われてきましたが、もしかするとその“徳”は、脳には当てはまらないかもしれません。
フランスの大規模な高齢者コホート(ESPRIT cohort)を対象とした最新の研究によると、「起床時間が早すぎたり遅すぎたりする人は、脳の記憶を司る“海馬”の体積が小さい傾向にある」ことが明らかになりました。
さらに、「不眠症状や睡眠の質の低下は、脳の血管の障害を示す“白質高信号(WMH)”の増加と関連している」という結果も。
💤 睡眠と脳構造の関係とは?
この研究では、65〜80歳の高齢者678人を対象に、MRI検査で脳の構造を可視化しました。
特に注目されたのは、
・海馬体積(記憶や学習に重要な脳部位)
・白質高信号(血管性の変化を反映し、認知症などのリスクの一因とされる)
の2つです。
これらと、起床時刻・就寝時刻・不眠症状・昼寝の習慣など、詳細な睡眠習慣との関連が分析されました。
☀️ 早起き・遅起きが海馬に悪影響?
研究で最も強く示されたのは、「起床時間が極端に早い(朝6時より前)または、遅い(朝8時以降)人は、海馬の体積が小さい」という結果でした。
つまり、脳の健康にとって“ちょうどよい”起床時間が存在する可能性があるのです。
また、不眠症状(入眠困難や中途覚醒など)が多い人は、脳の血管性病変が進んでいる可能性が高いことも判明しました。
😴 睡眠の質が血管性認知症リスクと関係?
不眠や睡眠の断片化(細切れになってしまうこと)、さらには特定の睡眠ステージ(レム睡眠、N2睡眠)の割合も、脳の血管の健康に影響していることが示唆されました。
特に、
・レム睡眠の割合が多い人は、白質高信号が少ない傾向
・N2睡眠の割合が多すぎる人や、周期性下肢運動が多い人は、白質高信号が多い傾向
といった、興味深い知見も見られました。
※REM睡眠:眠っている間に眼球がすばやく動く特徴があり、夢を見ることが多い時間。脳は覚醒に近いほど活発に働いており、記憶や感情の整理に重要だと考えられている。
※N2睡眠:浅い眠りから深い眠りに移行する中間の段階で、眠っている時間の約半分を占める。脳は少しずつ活動を落とし、外部からの刺激に反応しにくくなっていく時期。
🧩 睡眠が脳を守る“かぎ”になるかも
この研究は、睡眠のタイミングや質が、将来的な認知症リスクに関係する可能性を示しています。
特に、高齢期においては「規則正しく、質の良い睡眠をとること」が、脳を守る上で非常に重要であることが、改めて浮き彫りになったと言えるでしょう。
✅ 今日からできる“脳にやさしい”睡眠習慣
・起床時間は6〜8時の間に設定
・就寝は23時頃までに、なるべく毎日同じ時間に
・寝つきが悪い、夜中に何度も起きるなどの不眠症状がある場合は、早めに専門医に相談
・昼寝は30分以内にとどめる
・就寝前のスマホ使用やカフェイン接種は控えめに
🔍 この研究の限界点・注意事項
どんな研究にも限界があり、結果を解釈する上で注意事項があります。この研究の場合は、
・横断研究である→ 原因と結果の因果関係は明確にできない(例:睡眠が脳を変えるのか、脳の変化が睡眠に影響するのか不明)。
・睡眠指標の多くが自己申告に依存→ 主観的なバイアスの可能性(特に不眠症状や起床時間の記憶など)。
・高齢フランス人を対象としたコホート→ 結果が他の人種・文化・年齢層に一般化できるかは不明。
Cavaillès, C., Artero, S., Maller, J. J., Jaussent, I., & Dauvilliers, Y. (2025). Insomnia, early and late rising are associated with small hippocampal volume and large white matter hyperintensity burden. Alzheimer’s Research & Therapy, 17(75). https://doi.org/10.1186/s13195-025-01721-x